容子の場合
- [1] 容子 これで私を縛ってください
- 巻き戻されていく、ビデオの音を聞いて、緊張の糸が切れた私は、ずっと頭の後ろで組んでいた、両腕を解くとその場にへたり込んでしまった。
「まだ、おねんねにはちょっと早いぞ」
完全なる、敗北を認め床に崩れ落ちた私に、室田は冷酷な笑みを浮かべて言った。
「さあ、鮫島先生がお待ちだ」
室田は全裸のまま、床に伏せる私の腰に、手をかけ無理矢理立ち上がらせる。
「ああ・・・・・・」
私は、おぼつかない足取りで何とか立ち上がる。
乳房はふるふると切なげに揺れ、その真っ白な身体の中で唯一、黒々としている繊毛も悲しげに震えている。
その全てが、果てのない性地獄に堕ちようとしている、私の悲しい運命を象徴しているかのようだった。
「ああ、こ、こんな格好で、外に出なくてはいけないのですか」
拘束された身体で、表を歩かされる恐怖に身体が震えた。
「ふふ、心配するな。コートくらいはかけてやる。それに鮫島先生達は、同じビルの最上階の部屋にいらっしゃる。移動と言ってもエレベーターに乗って上に行くだけだ」
このビルには、いざという時の逃げ道である階段類も多く、その上、セキュリティーや防火管理も、しっかりしているため、鮫島も、この最上階にある部屋を隠れ家がわりにしているのだ。もちろん広さは室田の部屋とは比べものにならない。
「さあ、これを着るんだ」
室田は、そう言うと赤いハーフコートを、私の足元に投げ捨てた。
「あの、室田さん・・・・・・お願いがあるんです」足元のコートを着ようとはせず、言いにくそうに言うと、自分が持ってきたカバンに手を伸ばした。
「これで、私を縛ってください」
私が、カバンから取り出したのは、どす黒い色のロープだった。
「それは・・・・・・自分で用意してきたのか・・・・・・」
あまりの驚きに、うわずった声でそう尋ねた室田に、私はこっくりと頷いた。
「室田さん、正直に言いますわ・・・・・私、ここにくる前に、もしパンティーが濡れていなかったら、どんな手段を使ってでも貴方や、鮫島先生を告発してやろうと思って、ここまで来たんです」
告発と言う言葉を聞いた、室田は動揺していた。
「でも・・・・・もし・・パンティーが濡れていたら・・・・・・・私がマゾヒストだったら・・・・・・その時は・・もう私が逃げ出したいとか、逆らいたいとか思わないように・・・・・・このロープで両腕を縛り上げてもらおうと、これを持ってきたのです」
私は、呆気にとられる室田にロープを手渡し、ぐるりと回って背中を向ける。
吹き出物も染み、そばかすも、何一つない真っ白な背中だった。
「もう私が、逃げ出したいとか、迷わないように、このロープできつく私を、縛ってください」
私はそう言って、目を伏せると、ゆっくりとした動きで、呆気にとられている室田に背を向けたまま、その華奢な両手首を背中で交差させた。
「よっ、よし、いいだろう」
室田は動揺している自分を悟られないように、ゆっくりとした口調でそう言うと、重なり合う私の白い手首にロープをかけた。
「あ、あぁ」
自身の喘ぎ声が部屋に響く中、室田はロープで両手首をまとめると、そのまま、残りを私の大きく前に突き出した乳房の上下に回し、そのたわわな柔肉を絞り出した。
「ああ、室田さん。もっときつく縛ってください。これじゃ、私の決心が揺らいでしまいますわ」
私は、身動き一つできないほどに拘束されることで、キャスターとしての正義感やプライドを全て、押さえ込んでしまおうと思っていた。
「ああ、わかった」
室田もそんな私の、気持ちを察したのか、もう何も聞かず、一度ロープを緩めると今度は力一杯乳房を絞り出した。
「う、うぅぅ」
男の強い力で胸を締め上げられ、私は苦しさのあまり床に崩れ落ちた。
だが、瞳には妖しい光が宿り、顔はその苦しみ酔いしれるかのように恍惚としていた。
「どうだ、気分は」巨乳を揺らしながら、苦しそうに喘ぐ私を室田は心配そうに覗き込んだ。
「ああ、大丈夫です。行きましょう」
両腕をがっちりと緊縛されたまま、切なそうに身体をくねらせる私は、沸き上がる妖しい被虐の快楽に両膝を擦り合わせながら、ゆっくりと立ち上がると、うっとりとした瞳で室田を見上げた。
- [2] ベンジー
- へたり込んだ容子に、室田の追撃は厳しかったね。
でも、それ以上だったのが容子と言うわけだ。
「こんな格好で、外に出なくてはいけないのですか」とか言いながら、せっかく用意してくれたコートも着ないで、どす黒いロープを持ち出すとは。
室田がびっくりするのもムリはない。
そのロープで、しっかり縛られたか。
これでもう物理的には逃げられなくなってしまったね。
もうコートも着られないし、そのまま外に連れ出されるのかな。
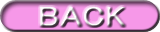 |